こうして、やっとミカエラとの話しがつき、彼女が通行証をしたためている間、外で馬に飼い葉と水の補給をしながら自らも一服していたシモンの傍に、イポーリトが近づいた
「父上に会ったんですよね。
それに、アンドレスにも!
二人共、お元気でしたか?」
大木の幹にもたれかかったまま、「ああ」と答えるシモンの傍で、イポーリトは眩しそうに遠くを見やった。
すっかり天頂高く上がった午後の陽光が、辺り一面に燦々と降り注いでいる。
見渡す限り、煌く残雪を冠した霊峰たちが連なるばかりだが、少年の真っ直ぐな瞳は、それらの山々を越えて遥か彼方に広がる大海までをも見晴るかしているかのようだ。
シモンの視線も、つられるようにして、そちらに動く。

その時、ふと、イポーリトが独り言でも呟くかのようにポツリと言った。
「アンドレスは、僕にとっては兄のような大切な存在だけど、でも、本当は、僕はアンドレスがずっと羨ましかったんです」
「え?」
突然、何を言い出すのかと、葉巻をくわえたまま少年を見据えるシモンを、イポーリトも、ちらっと見てから、また山の彼方へ向き直った。
「だって、アンドレスは僕よりたった6歳上なだけなのに、この戦さでは、たくさん活躍しているんです。
それは、もちろん、僕もすごく嬉しいけど、でも……」
イポーリトは言葉を濁して、僅かに地面に目を落とした。
「アンドレスは、この戦さが始まる前から、随分、父上から当てにされていて…。
アンドレスが僕くらいの年だった頃には、もう、父上は、アンドレスをあのアパサ殿の元に武術修行に行かせることも決めていたんです。
息子の僕がいるのに、父上は……」

思いがけない昔話しがはじまってしまい、シモンは、参ったなという表情でちょっと頭を掻いたが、思いの外、深刻めいた表情の少年を放置して去るもできず、大木の幹にもたれたまま足を組みなおした。
このようなこと父母兄弟には言えなかろうし、ざっと見渡しても、この戦場に同年代と思しき友になりそうな少年たちも見当たらない。
いたとしても、トゥパク・アマルの息子ともなると、なかなか胸襟を開いて思いを打ち明け合える相手など難しかろう。
「そんなことがあったとは知らなかったが、単純に考えても、その頃、まだ君は10歳にも満たない年齢だったんじゃないのか?
それに、あのトゥパク・アマル殿のことだから、多分、反乱前から役人に目を付けられていただろう。
そんな中で、自分の息子に軍事訓練まがいのことを施しているなんて見られたら、さすがに不味いだろう?
それで、敢えて、あまり目立たぬように、息子ではなく甥の方を――つまりアンドレス殿の方を行かせたんだろうよ」
そのシモンの言葉が聞こえているのかいないのか、嘆息混じりにイポーリトが続ける。
「アパサ殿の元で訓練を受けたアンドレスは、本当に、とっても強くなって帰ってきたんです」
それから、俯きがちになっていた眼差しを蒼天に向けると、大きく深呼吸をした。
澄んだ陽光を真上から浴びる少年の、ミカエラに似た綺麗な横顔は――思想的には理想主義的なところがあれども、基本的にはリアリストのシモンの目にさえ――瞬間、まるで本当の天使のごとくに錯覚させる。

やがて、少年が瞳を輝かせてこちらを振り向いた
「シモン殿は、アンドレスの戦場での戦いぶり、見たことがありますか?」
「え、いや」
「僕も直接は見たことが無いけど、兵たちの噂はたくさん聞いています。
最前線に立って、軍神のように勇敢に戦ってるって!!
サーベルを振るう姿は、まるで舞を舞っているかのように軽やかで美しかったと、話してくれた人もいます!」
そのイポーリトの表情は、我がことのように誇らしげで、深い敬愛の念に満ちている。
「それはまた、なかなか凄そうだな」
そう答えつつも、そのアンドレスだって、まだ二十歳前の若い将兵なれば、実際には色々と辛苦も舐めていることだろが、とシモンは胸の中で呟く。
増して、戦さは、武術が優れていればそれで良いというものでも無い――。
しかし、憧憬と敬慕と羨望と、様々な想いと葛藤に揺らいでいる少年を前にして、シモンは、今は黙って、ただ少年を見守った。
「それで、アンドレスは父上にも、ますます当てにされるようになっていったんです。
逆に、僕は、いつまでたっても子どものような扱いで…。
だって、この戦さがはじまった頃、クスコに父上が進軍した時も、父上はアンドレスを連れて行ったけど、僕はトゥンガスカの本陣で母上と留守番だったし。
それに、アンドレスが父上から2万もの兵を与えられて、ラ・プラタ副王領に遠征に出ていた頃だって、僕はまともに戦さに出ることさえ許されていなかった。
こうして今回だって、父上はアンドレスを沿岸部隊として英国艦隊との決戦に連れて行ったけど、僕はまた母上と留守番で……」
いつしか虚ろな眼差しになって視線を宙に漂わせたまま、イポーリトが止め処無く言い募る。

そんな彼の横顔を黙って見守っていたシモンだが、さすがに居た堪れない気分になってきて、口を挟んだ。
「それは、父上が君を当てにしていないということではなくて、むしろ、大事な息子を護ろうとしての采配であったように思えるが」
しかし、イポーリトは――え、何を言い出すのか?――という表情で、目元をキッと聳やかした。
そんな少年の方に、シモンは沈着な調子でゆっくりと説明していく。
「つまり、今、君が話した通りなら、アンドレス殿は、トゥパク・アマル殿にとって血縁者ではあっても、あくまで部下というか軍兵としての扱いだ。
だが、イポーリト殿はやはり大切な皇子。
安易に最前線に立たせたりはできないだろう?
トゥパク・アマル殿とて、一人の親だったってことさ。
増してや、時が時なら、君はインカ皇帝の皇位継承者なのだし、いや、直系の皇帝末裔であることには今も変わりはあるまい。
ならば、なおさら、そう容易(たやす)く命を落として良い立場や身分ではなかろう。
トゥパク・アマル殿が、イポーリト殿を前線から離れたところに大切に匿い、庇護しようと思うのは、指揮官としても、父親としても、むしろ妥当な判断だと思うが」
「いいえ!!
父上は、息子であるとか、そうでないとかで、分け隔てをする人ではないんです!
強ければ、息子であろうがなかろうが、区別すること無く、最前線で戦わせるはずです!!」

「――…」
イポーリトの険しい表情と激しい口調に、先刻のミカエラとのやり取りが脳裏をかすめ、シモンは思わず口をつぐんだ。
そんなシモンの方へ、イポーリトが、ぐっと、大きく一歩を踏み込んだ。
「だけど、さっきのあなたの母上との話を聞いて、僕がここに残っていることにも意味があるんだって少しは思えたんです。
あなたが言ったように、今、この陣営は、父上も、アンドレスも、ディエゴも、他の主だった将兵もみんな出払っている。
あ、ベルムデスは、あんなふうに穏やかそうに見えても、腕っ節も凄く強いんですけどね。
だけど、なにぶん、歳をとっているので。
だから、もし、ここに敵襲があれば、今度こそ、僕は命のあらん限り精一杯に戦って、母上も、この陣営も、守りたい!
今度こそ…!!」
「――その意気込みは、立派だとは思うが……」
語気強く語るイポーリトに、ここまでの会話から気持ちは察せられるとはいえ、やはり現実的にはまだ子どものような年齢に過ぎない少年のそのような台詞に、シモンは複雑な思いを否めず、無意識に唇を噛んだ。
「なあ、もう少し肩の力を抜いたらどうだ?
今からそんなに力(りき)んでいたら、本番戦までもたないぞ」
場の空気を変えようと、少々冗談めかして肩をすぼめたシモンをあっさり遮って、「あなたも知っているとは思うけど」と、再びイポーリトの思いつめた声が響き渡る。
強まってきた冷風に絹のような黒髪をなぶらせ、漆黒の瞳を苦しげに微動させながら、少年は相手を真正面から見上げた。
「かつてトゥンガスカの本陣戦で、父上が捕われた後、インカ軍はあえなく総崩れになりました。
――無残な敗退だった……!
しかも、僕は、あの時だけは、父上と一緒にあの陣営にいたんです!!
なのに、僕は、父上のためにも、インカ軍のためにも、何ひとつできなくて……!」
そう言って、目の前の少年の顔がみるみる苦渋に歪んでいくのを見つめながら、シモンも眉根を寄せた。
「そんなに自分を追い込むなよ。
第一、あの時は、あそこにディエゴもいたろう?
他の将兵だって、たくさんいたはずだ。
そんなに自分を責めることもあるまい?」
「それだけじゃないんだ!!」
じわりとイポーリトの目元に悔し涙が膨れ上がった。
「本陣を脱出して、母上やフェルナンドと一緒に、敵の追跡から逃れる旅をしていた時も、結局、追いついてきた奴らに取り囲まれて!
だけど、僕は、母上をお守りすることができなかった…!
挙句、母上も、フェルナンドも、僕も、捕まって、地下牢に入れられて、散々な目に合わされて……。
もし、父上が助けに来てくれなければ、あのまま母上も、あんなに小さなフェルナンドさえも、処刑台に引き摺り出されていたかもしれない……!!」

「――……」
トゥパク・アマルを思わせる切れ長の目をひどく険しくしながら、大粒の涙の零れる瞳を激しく揺らしているイポーリトを前にして、普段は感情を動かされることの殆ど無いシモンも、にわかに胸詰まる思いに憑かれずにはいられなかった。
――まだ、たかだか12〜13歳の子どもであり、周りの大人は彼を保護の対象と思いこそすれ、戦力としての期待なぞしてはこなかったことだろう。
だが、本人は、一人前の、否、それ以上の重責を感じてきたのだ。
その分、その心に残された戦さの爪跡はいっそう深かろう……。
しかも、まさか、一見、年端に似合わぬほどに大人びて沈着に見えるこの少年が、実は、年齢よりも幼いほどに、ひどく純真で脆い心を抱え、このようにまで激しく悔恨の念に苛まれていようなどと――周囲の大人たちのどれほどが気付いていることだろうか。
いや、恐らく、察しようもないのではないか。
そのような思いに捕われているシモンの傍から、イポーリトの強い決意を宿した声音が聞こえてくる。
「それに、父上がここを発つ前、軍議の席で皆の前で言っていたことを思い出したんです。
『わたしのいない間、母上をしかと助けよ』、『母上を頼んだぞ』って!
だから、もし、本当にあなたの言うように、ここに敵襲があったなら、今度こそ、僕は、母上も、この陣営も、絶対に守ってみせる!!」

噛み締めるように決然と語るイポーリトの、大分逞しくなってきたようで、それでいて、まだか細いような、そんな不安定な肩をシモンはグッと握り締めた。
「なかなか、いい気概だ。
だが、本当に用心することだ。
英国艦隊との海戦の火蓋が既に切られ、クスコでも決戦が始まった今こそが、最も危険なんだ。
さっきの話は、今、この瞬間にこそ、実際に起こる可能性が――」
ハッとシモンが言い止(さ)した時、血相を変えたインカ兵たちが数名、息堰切って向こうから走ってきたかと思いきや、ただならぬ勢いでミカエラのいる天幕へと飛び込んで行った。
「――!」
シモンも、イポーリトも、瞬時に嫌な予感に憑かれ、そろってそちらを凝視する。
張り詰めた短い沈黙が流れ、やがて低く絞ったシモンの声がイポーリトの耳に聞こえてくる。
「今、ミカエラ殿の天幕へ走り込んでいった兵士たちは、何者だ?
たいそうな慌てぶりだったが。
まさかとは思うが、君たちが放ったインカ軍の斥候なぞではなかろうな?
だとしたら……」

「恐らく、シモン殿のお察しの通りでしょう。
実際、あの者たちは、この陣営の斥候たちなんです。
不意の敵襲に備え、僕たちは、この陣営の山麓の方まで、たくさんの斥候を放っているんです」
イポーリトは、サッと手の甲で素早く涙を拭い去ると、急に大人びた表情と口調に戻ってそう答え、ミカエラのいる天幕の方へと足早に歩み出した。
「まじで斥候!?
って、ことは――え、やっぱり、そういうことか?!
まずいだろ、それ…!
おい、待てよ!!」
シモンはさすがに慌てた声を上げながら、イポーリトの後ろ姿と、それから、木陰でくつろいでいる己の愛馬とを見交わした。
馬は、すっかり飼い葉を平らげて満足そうにしており、いつでも旅立てるよと言わんばかりの目でシモンを見下ろしている。
「ったく、いくらなんだって、こんなタイミングでっ」と、思わずシモンは吐き捨てた。
それから、やむなくイポーリトの後を追いかける。
ほどなく二人がミカエラのいる天幕に足を踏み入れると、中は不気味なほどに静まりかえっていた。
明るい陽光の下から戻ったばかりのせいか、天幕の中は先刻よりもずっと薄暗く感じられる。
その暗さに慣れぬ目を凝らしながら、シモンは内部を見渡した。
天幕の奥では、既にミカエラが斥候たちの報告を聴き終えた後らしく、毅然とも愕然とも見える様相で椅子から立ち上がっていた。
テーブル上には、彼女がしたためたばかりと思しき通行証が、まだインクも乾ききらぬままに置かれている。

一方、シモンとイポーリトが天幕の中へと戻ってきたことに気付くと、ミカエラは、先にも増して研ぎ澄まされた、氷刃の如く鋭い美貌を、シモンへと向けた。
「そなたの忠告してくれた通りになってしまいました。
スペイン軍が、当陣営を目指して迫り来ていると、たった今、斥候から報告を受けたところです」
やっぱりか!――シモンは胸の内で呟き、反射的に己の頭髪を片手でガッと掻き毟った。
(それにしたって、これは、いかにも不味い事態じゃないのか?
打つ手はあんのかよ……?!
もっと早ければ、一時的にでも、増援部隊を呼び寄せることができたかもしれない。
実際は、どの戦場も手一杯で援軍を出す余力などなかろうが、それでも、ミカエラ殿や皇子がいるここになら、他所で無理をしてでも遣り繰りして兵を送ってきただろう。
だが、それも、もう遅すぎる…!)
思わず溜め息の出そうになるのを堪えて、シモンは、いっそう薄暗い天幕の奥まで戻っていく。
そうしながら、己の横を、いかにも姿勢正しく、スラリと成長した長い足を力強く歩ませている少年の横顔に、チラリと視線を走らせた。
イポーリトは僅かに頬を紅潮させながら、目元を厳しくして、凛々しく唇を引き結んでいる。
しかし、その端正な横顔は冷静で、先刻まで、あれほどボロボロと涙を流しながら心の内を訴えていた痕跡は、どこにも残っていなかった。
とはいえ、その腰の帯剣を握り締める褐色の指先には、剣が微動するほどに、不自然に力が入りすぎてはいたのだが……。

その時、バッと、背後で天幕入り口の垂れ布が大きく跳ね上げられて、数名のいかにも屈強そうなインカ兵たちが雪崩れ込んできた。
兵たちはミカエラの方へ跪いて敏捷に礼を払うと、即座に立ち上がって、彼女と皇子と、そして、傍のベルムデスを護るが如く、彼らを堅固に取り囲んだ。
護衛兵か各部隊の隊長たちか?――と、シモンが見やっている間にも、兵たちはミカエラやイポーリトを囲んだまま、険しく深刻な形相で息堰切ってがなり出した。
「ミカエラ様、敵襲とのこと、如何がいたしましょう?!」
ミカエラは、「落ち着きなさい。敵がここに辿り着くまで、まだ数時間はかかります」と、毅然と言い放つと、天幕の一隅に残っていた斥候たちを鋭く振り返った。
「それで、そなたたちが偵察してきた敵兵の数は、いかほどですか?」
斥候たちは急峻な山道を余程急いで戻ってきたのであろう、まだ喉をゼイゼイさせながら、運ばれてきた水を貪るようにあおっている。
が、ミカエラの問いに、彼らは、サッと深く畏まって彼女に向き直った。
「はっ、ミカエラ様!!
ざっと3千ほどはいるかと」
「3千……!
各地に、あれ程、敵の兵力を分散させてきたというのに、よくも、まだそのような数を当地のためだけに割けたものね」
深く眉間に皺を寄せたミカエラを、シモンが見やった。
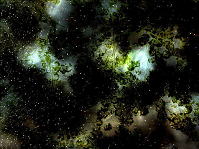
「ミカエラ殿、ここには、あなたもイポーリト殿もいる。
多分、他の二人の皇子も、ここにいることだろうし、ならば、敵側にとって、こんなに旨味のある場所はない。
さっきも言った通り、あなたや皇子さえ捕らえてしまえば、いくらでもトゥパク・アマル殿に脅しをかけることもできるのだから、敵がそのくらいの兵力を投入してくるのは当然でしょう。
いや、むしろ、こんな要衝地に対して3千とは、少ないくらいだと思うが?
それだけ敵方も兵力が不足している、つまりは、あなた方が上手く敵を翻弄していることの証しでもありましょう」
「褒めてくださって、ありがとう」と、ミカエラは感情の伴わぬ声で答え、やや青ざめた唇にしなやかな指先を添えた。
「ですが、わたくしたちにとっては、3千の敵とて、決して少ない数ではないのです」
「今、この陣営で敵を迎え撃てる戦力は、どれほどなのです?」
そう問うシモンも、真顔である。
「2千…いえ、実戦に耐える兵は、千7〜8百ほどかしら。
ここで訓練中の義勇兵たちも数百人はいるけれど、彼らは、まだ戦線に出て戦うには危険すぎる」
「それじゃ、敵の3分の2未満どころか、約半数じゃないか…!
いくらなんでも、あなたや皇子がいる陣営としては、その数は手薄に過ぎる。
そんな偏った采配を、トゥパク・アマル殿が許したのですか?」
そう、思わず口走ってしまってから、シモンは口をつぐんだ。
(今さら、そんなことをボヤいても何にもならないが…!
しかし、口惜しいことだが、こいつは、あのアレッチェの方が、国中に散らした兵の配分も、結局は上手(うわて)だったと言わざるを得まい)

一方、ミカエラは、「いいえ」と僅かに首を振った。
「あの人がここを発つ頃には、この陣営にも、もっと多数の兵力が残されていました。
でも、この数日で、各地の戦線が一挙に広がり、この陣営にばかり兵を留めておくわけにはいかなくなったのです」
シモンは苦々しく奥歯を噛んだが、すぐに斥候の方へと、やや厳しい目を向けた。
「それにしても、敵軍は、もう山麓まで迫り来ているというじゃないか?
気付くのが遅くはないか?
3千もの大軍が押し寄せてきていたのなら、もっと早い段階で気付いてもよさそうなものだ。
早ければ、打つ手もあったろうに。
あと数時間で押し寄せられては、まともに迎え撃つ準備もままならんではないか」
厳つい胸板を上下させながら、まだかなり息の上がった状態のまま、斥候たちはジロリとシモンを睨んだ。
「心外なことを言うな!第一、この見知らん白人は何者なのだ?!」――と、言わんばかりの、いかにも剣のある眼である。
そして、シモンを睨(ね)め付けながら、きっぱりと言い返す。
「もちろん3千の大軍が向ってきていれば、ずっと早くに気付けていた!
だが、奴らは、この近くまで、わざと小隊に分かれて、我々の目をかすめながら進軍してきたに違いないのだ。
山麓まで迫ってきてから、結集しやがったんだ!!
ちくしょう……!!」

シモンは、悔しそうに床を拳で叩いている斥候から視線をはずし、今度は、ミカエラに改めて向き直る。
「ミカエラ殿、さすがに多勢に無勢だ。
このようなことを言いたくはないが、いっそのこと、この陣営は見放し、敵が到達する前に早急に全員が撤退するという道もある。
わたしが、あなたの立場なら、躊躇なくそうするでしょう」
しかし、ミカエラは唇を噛み締めて、首を振った。
「いいえ。
撤退することはできません」
「ミカエラ殿!」
シモンはグッと身を乗り出し、ミカエラを厳しく睨んだ。
「今は、プライドや意地を通している場合ではありませんよ。
多数の兵の命が懸かっている上に、本当にあなたがたが捕われでもしたら、ここまで反乱を広げてきたトゥパク・アマル殿の苦労はどうなるんです?」
「そうではないのです」と、ミカエラは睫毛を伏せて口惜しげに呻くと、スラリと長い指先で額を押さえ込んだ。
「撤退しようにも、することができないのです。
今、敵が迫り来る東斜面の反対側に、本来なら退路として確保していた西側斜面の途上の河川が、先週の豪雨で氾濫し、今は渡れない状態なのです」

「――!
ってことは、退路さえも無いってことか…!!」
シモンは頭をガシガシといよいよ激しく掻き毟って、地から突き上げるような深い息を吐いた。
「なるほどね。
敵さんも、それを見越して、意気揚々と攻め込んで来たというわけか」
いっそう重苦しい沈黙が天幕の中を支配する。
だが、その時、不意にイポーリトの声が天幕に響いた。
「ならば、やはり、戦うしかないのではないですか?
どんなに相手が多勢でも、決死の覚悟で戦えば、きっと活路は開けるはずです」

ハッと皆の視線が一斉に集中する中、イポーリトは、大人顔負けの沈着な面差しと鋭利な眼光で周囲の者たちを見返している。
そして、皆を説得するかの如く、一語一語噛み含めるように続けていく。
「母上も、皆の者たちも、逃げ道が無いのならば、正々堂々と戦うしかありますまい。
もしここに父上がいたら、父上も、きっとそう仰るに違いありません!
それに、こうしている間にも、スペイン軍は着々と迫り来ているはずです。
今、一刻を争う中で僕たちが話し合わなきゃいけないことは、どうやって彼らと戦うか、その方法ではありませんか?」
「イポーリト……」
見つめるミカエラの視界の中で、イポーリトは、あくまで冷静な表情に、敢然とした覚悟をも宿し、周囲の大人たちを圧倒する気迫を放っている。
だが、母たるミカエラの目は、そのような息子の中に潜む、戦さへ逸(はや)る利己心や恍惚感の如きものをも見逃さない。
ミカエラは、頼もしさだけではおさまり切らぬ、それら非常に危ういものを瞬時に見透かして、強く眉を顰(ひそ)めた。
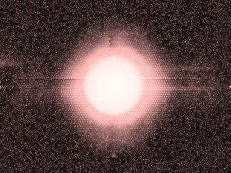
しかしながら、周囲のインカ兵たちは厳めしい体躯を翻し、意気揚々とイポーリトの周囲に跪いた。
「イポーリト様!
さすがはトゥパク・アマル様の御子息様であられます!!」
「はい、イポーリト様!!
きっとトゥパク・アマル様も、あなた様と同じように仰いましょうぞ。
それに、如何に我が兵の数が劣勢でありましょうとも、この陣営の専門兵たちは選り抜きの精鋭ばかりです。
増してや、ここには、あなた様やミカエラ様もいらっしゃる。
必ずやインカの神々のご加護もありましょう!
存分に戦って、奴らに我らの真の底力を見せつけてやりましょうぞ!!」
屈強な兵たちに傅(かしず)かれ、凛々しく頷き返すイポーリトと、そして、複雑な表情を隠せぬミカエラの双方を見やってから、シモンはテーブルに座したまま黙って状況を見守っていたベルムデスに目を留めた。
「ベルムデス殿」
「どうやら戦さは避けられんようですな」
平素の温厚な気配を保ちながらも、厳しい表情で顎を擦っているベルムデスへと、シモンも真っ直ぐ頷いた。

そして、相手の傍に広げられていた地勢図を覗き込む。
「さすがに敵方も、こんな急峻な山道を多くの大砲まで運んできているとは考えにくいですが、少なくとも大量の銃や弾薬を携えてきていることは間違いないでしょう。
今さら、わたしが言うまでもありませんが、敵の火力を封じるには、どのみち接近戦に持ち込むしか方法はありません」
ベルムデスも、おもむろに頷き返した。
それから、厳つい褐色の指先で地勢図上の東斜面をなぞりながら、低く響く沈着な声音で語りだす。
「シモン殿、あなたの仰るように、これほどに険しい山岳地ゆえ、如何に相手の数が多いとはいえ、実際に彼らが攻め上ってくることが可能な斜面は限られておるのです。
せいぜい、この数メートル幅の細長い道無き道を、長々しい縦列を為して登ってくることしかできないはずです。
つまり、当地は、敵が、その数を、そう容易(たやす)く生かせるような地形ではないのですよ。
トゥパク・アマル様が、ここに本陣を敷いた最たる理由もそこにあったのです」
ゆるぎない口調でそう言うと、ベルムデスは鋭さのいや増した面持ちを上げた。

「なるほど」
シモンはベルムデスに頷きながら、数回、己の額を拳で叩(はた)いた。
それから、地勢図を睨みながら、いっそうテーブル上に身を乗り出す。
いつしか、そんなシモンとベルムデスの周りに他の者たちも集まり、息を詰めて二人の話に耳を傾けている。
その張り詰めた空気の中、「そういうことならば」と、再びシモンが口火を切った。
「敵を迎え撃つ方策が、無いでも無い。
というより、この状況では、むしろ選択肢は限られている……。
まず、味方の兵力を大きく二つに分ける。
敵の先頭部隊を迎え撃つための少数の精鋭は、ここの山上の陣営に残ってもらう。
そして、あとの主力部隊はこの陣営から離れ、敵に気付かれぬよう森林を利用して、登り来る敵の縦列の両翼に回るのです。
この陣営に残った少数部隊は、攻め上ってくる敵の先頭集団を、斜面を登り切ってくる小隊ごとに各個に撃破しながら、当陣営への侵入を断固として阻止。
そちらに敵の意識を引きつけておいた上で、機を見て、残りの主力部隊は、進軍途上の敵の隊列に奇襲をかける。
一気に敵の混乱を煽り、両翼から挟み撃ちして殲滅させるのです」
一息にそう言い切ると、シモンは地勢図から顔を上げ、「単純な戦法だが、わたしに思い付くのは、このくらいです」と、肩を竦める。

他方、周囲に集まった厳ついインカ兵たちは、ゴクリと生唾を呑みくだした。
「それでは、主力部隊は、はじめから肉弾戦を強いられることになる……!」
シモンは厳しい表情で、低く答える。
「敵の持つ圧倒的な火器の威力を封じるには、それしかありません」
その時、不意に、「ちょっと、待って」と、ミカエラの険しくも凛とした声が背後で響いた。
「敵の両翼に回ると簡単に言うけれど、あの斜面は急峻で、まともに歩くことさえ難しいのよ」
ミカエラの言葉に、しかし、シモンは、あっさりと切り返す。
「だからこそ、奇襲が成り立つのです。
まさか、あのような急激な斜面のどこかから、敵襲があろうとは向こうも思ってはいないはずだ――そこを突くのです。
それに、あなたたちインカ軍の機敏な運動能力なら、命懸けでやって、できないことはないはずだ。
ミカエラ殿、あなたなら悟っていることと思うが、これだけ兵力に差があっては、正攻法でぶつかって行っても、勝機はまず無い」
そこまで言うと、シモンは、地勢図の脇に置かれていた通行証を、素早く手に取った。
そして、ミカエラの方へ顔を上げて、硬い声で飄々と言う。
「まあ、いずれにしろ、どのような戦略を取るか、それを決めるのはあなた方です。
わたしは、あなた方も知っての通り、リマに急ぐ身なのでね」
「――!!」
ミカエラとイポーリトが、不意を突かれたように、目を見張ってシモンを凝視する。
そんな二人の様子に頓着することもなく、シモンは、サッと、懐に深く通行証をしまい込むと、何の躊躇(ためら)いも無い足取りで天幕の出口へと向い始めた。
その取り付く島もないシモンの態度に、ミカエラもイポーリトも、ただ去り行く相手の後ろ姿を凝視したまま、にわかには何も反応できずにいる。
一方、己の背に二人の強い視線を感じたのか、シモンは天幕の出口で垂れ布を持ち上げながら、最後にチラリとこちらを振り返った。
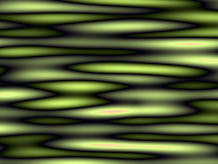
「まさか、わたしの戦力を援軍として、当てになどしていませんでしたよね?
こちらも、これからリマに向かいながら、順次、各地の同志たちと合流していく予定でしてね。
だから、わたしの元にいる兵は、今はまだ、それこそ7〜8百やそこいらの少数に過ぎないのです。
わたしだって、あなた方を援護して共に戦いたい気持ちは山々だが、援軍として役に立てるどころか、こちらまで、まとめて一掃されてしまうのがオチだ。
申し訳ないが、今、共倒れするわけにはいかないのです」
あっさりと言い残して、さっさと天幕の向こうへと姿を消してしまったシモンを、ミカエラもイポーリトも絶句したまま、ただ呆然と見送るばかりである。
が、ハッと我を取り戻したイポーリトが、ダッと、駆け出した。
そして、天幕を飛び出すと、手早く馬の縄を解いて今にも駆け去りそうなシモンの後ろへ走り寄った。
「シモン殿!!
本当に、このまま行ってしまうのですか?!」
馬の手綱を手に、シモンはイポーリトに背を向けたまま、さっさと軍門に向って歩き出す。
「本当も何も、元々、ここにはリマへの通行証をもらいに立ち寄っただけだ。
さんざん引き止められて、こっちも時間が足りなくなっているんだ。
その上、こちらの命まで危うくさせられては、たまらん」
「そんな……!!」

イポーリトは、シモンの前に回り込むと、必死の形相でそこに立ちはだかった。
「僕たちを見捨てるのですか?!
シモン殿!!
あなたは、そんな人ではないはずだ!!
今、あなたの元には7〜8百の兵がいると言いましたよね?
合流してくれれば、敵の3千に対して、僕たちも2千5百近くになれる!
もしあなたが援軍になってくれれば、どんなに心強いか……!!」
しかし、シモンは、イポーリトをグイッと冷たく脇に押し退けると、さっさと馬に飛び乗った。
そして、相手を厳しい顔で見下ろす。
「甘ったれるな!!
さっき、君は、この陣営を自分の手で守ってみせると、あれほどハッキリと言っていたじゃないか!
あれは、ただの口から出まかせか?」
「……――!!」
「本気でああ言ったのなら、自分の力で、それを証明してみせろ!!
しっかりと見届けてやる。
――遠くからな!!」
そう言い残すと、シモンは、鋭い掛け声と共に、一気に馬を駆り出した。
その後ろ姿は、遠のく蹄音と共に、たちまち急峻な山道の向こうへと消えていく。
先刻にも増して冷たい風の吹きすさぶ中、涙の滲む目元を愕然と見開いて立ち尽くす、儚げな少年の姿だけが残された。
ひどく裏切られたような傷心を抱えながら、イポーリトは重い足取りで天幕の中に引き返していく。
中には、先にも増して多数の部隊長たちが寄り集まっており、張り詰めた空気の中、ミカエラやベルムデスを中心に着々と作戦会議が進められていた。
彼の弟たち――2歳下の次男マリアノと4歳下の末子フェルナンドも、いつしかそこに姿を現しており、戻ってきた兄の姿を見つけると素早く傍に駆け寄ってきた。
ミカエラ似の自分に対して、トゥパク・アマルを生き写したかのような愛らしくも凛々しいマリアノ、そして、まだ10歳にも満たぬ、天使のような風貌を宿した幼いフェルナンド――そんな二人とも、今は強い不安の色を滲ませている。
「兄上!!」
「スペイン軍が攻めてきたって……!」

イポーリトは己の心痛を押し込めると、サッと姿勢を正して、弟たちに逞しい笑顔をつくって見せる。
そして、自分の両脇に身を寄せてきた弟たちの腕に両手を回し、力強く抱き寄せた。
「案ずるな。
僕がついてる!」
「兄上…!!」
いっそう己に強く身を寄せてくる、まだ、せいぜい己の肩や胸の高さほどもない背丈の弟たち。
そんな二人が大きく瞳を揺らしながら一心に自分を見上げている姿を見下ろしているうちに、イポーリトは己の全身に再び熱い血が巡りはじめるのを感じていた。
(そうだ……!
人を当てにしようだなんて、そんなんじゃ、今までと何も変わらないじゃないか!
それに、他に助けてくれる人がいないなら、どのみち、無理矢理にだって自分がしっかりしなくちゃ駄目じゃないか!)
そう心で力強く己に語りかけながら、しかし、次の瞬間には、不意に別の不安げな思いが胸中にジワリと広がっていく。
(どんなことをしてでも、この戦いを乗り切らなくちゃいけない…!
だって、そうしなきゃ、そうしなきゃ…僕たちも、兵たちも、皆、どうなってしまうんだ?
本当にスペイン軍が攻め込んできて、味方の数の少ない僕たちは奴らにどんどん撃ち殺されて……?)
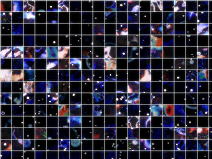
イポーリトの背筋にゾクッと寒気が走った。
(――そ、その果ては、どうなる?
全員が皆殺しにされてしまうのか?!
仮に生き延びたとして、捕虜として囚われて、またあの生き地獄を味わうのか?!)
瞬間、彼の胸に、これまで感じたことのないような激しい切迫感と戦慄が突き上げた。
「――!!」
思わず弟たちの肩を抱く手が大きくわななき、そんな兄をマリアノがハッと心配そうに見上げた。
「兄上…?」
勘の鋭いマリアノに己の内心を悟らせてはいけないと、イポーリトはサッと首を振った。
そして、すぐに無理に笑みをつくって、「大丈夫だ」と何事も無かったように応じる。
が、その内心では、先の一瞬、父トゥパク・アマルやアンドレスたちの思いに、微かながらも初めて、しかし、ひどく生々しく、触れたような感覚に憑かれていた。
無数の守るべき命を抱えて陣頭指揮を執らねばならない彼らの心中――それは、イポーリトが今まで思い描いていたような勇壮で血潮の昂ぶるようなものとは、全く異なる種類のものだった。

イポーリトは動悸の速まるのを懸命にひた隠して弟たちの腕を放すと、早口で言葉を交わしながら作戦を詰めているミカエラたちの方へと戻りかけた。
その時、背後から、不意にマリアノの声が聞こえた。
「兄上、どうか一人で悩まないで…!
僕だって、みんなの力になりたい。
兄上の役に立ちたいんだ……!」
去りかけていたイポーリトの足が、その場に止まる。
振り返ると、唇を強く噛み締めたマリアノが、真っ直ぐな眼差しをこちらに向けていた。
「マリアノ……」
やはり、勘の鋭いマリアノに動揺する己の心を見透かされていたのかと、イポーリトは身を強張らせて、グッと言葉に詰まった。
しかし、良く見れば、自分を見つめるマリアノの瞳は潤んで大きく揺らいでおり、そこには縋(すが)りつくような必死ささえもうかがえる。
平素から、イポーリトは、この弟のことを、外見も内面もいっそう父トゥパク・アマルに似て、自分よりも勇敢で利発であると心密かに思い続けてきた。
かつてトゥンガスカの本陣戦で敵軍に破れたあの極限状況においてさえ、追っ手の目をかすめるために母や兄弟から一人離れて別行動をすることを自ら申し出たのも、このマリアノだった。

だが、そんなマリアノが、今は、震えながら泣き出しそうなほどに、とても儚く、脆(もろ)く見える。
普段はあれほど勇敢な弟でさえも、この状況下に置かれては、強度の恐怖や不安に襲われずにはいられないのだ。
それにもかかわらず、健気(けなげ)にも、こんな兄を懸命に支えようとしている……!!
イポーリトの胸中に、愛しさと切なさが激しく込み上げた。
彼は突き動かされるようにマリアノの傍に歩み寄り、両腕でしっかりと相手の体を抱き締める。
突然のことに驚いて、マリアノが僅かに身じろぎした。
「――兄上……」
「ありがとう、マリアノ。
共に、この陣営を、そして、母上をお守りしよう!
そして、父上に笑顔で勝利のご報告をするんだ…必ず!!」
「はい!!
兄上……!」
自分の頬に触れているマリアノの頬が微かに濡れているのを感じながら、イポーリトはいっそう強く抱き締める。
その時、二人の兄たちの様子を、潤んだ瞳をいっぱいに見開いて見つめていたフェルナンドが、いよいよ大きくしゃくりあげた。
そんな末弟の気配に気づいて、イポーリトは、その小さな弟の体をも同時にしかと抱き寄せる。
弟たちの確かな息遣いを胸に感じながら、今一度、イポーリトは心に強く誓った。
(必ず守ってみせる…どんなことをしてでも――!!)

暫し抱き合った後、ゆっくりと弟たちを腕から放して二人に笑みを返し、イポーリトは作戦に沿って兵力の采配を淀みなく行っているミカエラの傍へと戻って行く。
素早く耳を傾けると、どうやらシモンが告げた戦略がおおかた採用されているらしかった。
イポーリトの脳裏を先刻のシモンの冷ややかな態度がよぎり、ズキッと刺し込む胸の痛みが突き上げる。
とはいえ、他に妙案が浮かぶでもなく、彼はただ苦々しく唇を噛み締めた。
かくしてシモンの策では、まず味方の兵力を二つ――少人数から成る精鋭部隊と残りの主力部隊――に分ける。
そして、小数部隊は、この山上の陣営に残り、山を攻め上り来る敵の先頭集団を各部隊ごとに各個撃破しながら陣営への侵入を阻止。
対する主力部隊は、左右の山間に潜み、敵の意識を少数部隊が引き付けている隙に、敵軍を奇襲挟撃するというものであった。
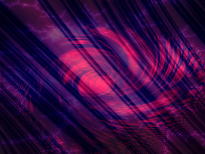
シモンの言い残していった作戦を頭で反芻しながら、イポーリトは胸の内で呟いた。
(この作戦を採用すれば、当陣営に残った少数部隊は、上方から大砲や飛び道具を使って敵を迎撃できるけど、それに対して、奇襲に回る主力部隊は体当たりの肉弾戦を強いられることになる。
だけど、スペイン軍の火力を封じるには、彼らの中に雪崩れ込んで接近戦を挑むしかないんだ。
それに、戦闘に耐える兵士の数も約半数と劣勢な僕たちインカ側には、思い切った奇襲攻撃はやむを得ない……)
この反乱が幕を開けて以来、ミカエラと共に本陣にいることの多かったイポーリトは、各地で無数に展開され続けてきた数々の戦闘行為の経過から顛末まで、様々な情報をつぶさに耳にしてきた。
その結果、元々、父母に似て利発さも備えいてた彼は、誰に指南を受けるでもなく、いつしか用兵術を自然に体得し、ある程度の戦略なら、その有効性を吟味できるまでになっていたのだった。

その時、ふとミカエラと目が合った。
「イポーリト、マリアノ、フェルナンド、そなたたちは、わたくしと共に、この陣営に残り、攻め込んでくる敵の先頭部隊を迎え撃ちます」
この事態に至ってもなお、決して感情のぶれを表に見せることなく、隙無く凛然としたミカエラの面差しを、イポーリトは、じっと見つめた。
(母上だって、本当は不安が無いはずは無いのに……!)
そんな思いが心に押し寄せてくるのを、彼はすかさず振り払った。
それから、真っ直ぐに問いかける。
その表情は、息子というよりも、もはや一人の戦士のそれである。
「母上!
では、母上も、マリアノたちも、僕も、全員がここに残るということですか?
それでは、誰が、奇襲部隊に同行するのですか?」
「奇襲部隊については、部隊長たちに任せます。
その采配も既に済んでいます。
イポーリト、そなたが案じることではありません」

イポーリトの内心を悟っていてか否か、いずれにしろ、ミカエラは事務的に、且つ、有無を言わさぬ口調できっぱりと言い切ると、早々に別の者への指示へと移っていった。
「待ってください、母上!!
それなら、その隊長たちと共に、僕も奇襲部隊に加わります!!」
背後から決然と響いたイポーリトの声に、ミカエラはハッと振り向いた。
他の兵たちも、一斉にそちらを振り返る。
「ここには、母上や、そして、マリアノやフェルナンドも残ってくれるのでしょう?
それに、少数部隊とはいえ、母上たちには精鋭の兵たちもついているし、ここには接近戦に出るには早すぎる訓練中の義勇兵たちだって残っています。
もちろん、ここもとても危険だけど、奇襲部隊はもろに白兵戦となって、もっと危険です。
それを、ただ他の兵や隊長たちにだけ、行けとは言えません!
僕も、一緒に行きます!!」
「イポーリト……!」
己の言葉に真っ向から対峙してきた息子に目元を険しくしながらも、それ以上に、驚きと息子の身の危険を案ずる母としての動揺が込み上げ、さすがのミカエラも即座には返す言葉に窮して凝固する。
その時、隊長たちの中から、ひときわ貫禄のある厳つい体躯の兵が前に出て、ミカエラの方へと深く平伏してから、強い覚悟を宿した顔を上げた。
「ミカエラ様!!
打ち首を覚悟で申し上げます!!
今や、劣勢な我らには退路すら無く、文字通り背水の陣にございます。
この一戦が、この陣営にいる全ての兵たちの生死を分かつことになりましょう。
限られた兵力で、もはや死戦をも覚悟で臨む戦さゆえ、兵たちがどれほど気概高く臨めるかに、この戦さ、勝敗の行方がかかっていると言っても過言ではございません。
イポーリト様が凛々しくも仰ってくださいました通り、もし皇子様が我らとご同行頂けましたなら、兵たちの士気は大いに高まることは間違いございません!!」
そう言い放って、地に額を擦りつけ、その場に沈むほどに深々と平伏している兵の傍に、イポーリトも駆け寄った。
そして、そこに膝をついてミカエラを見上げ、決然と言う。
「母上、お願いいたします!!
僕も、皆と共に戦いに行かせてください!!」
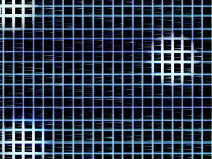
「……――!!」
言葉を失ったまま見下ろすミカエラの視界の中で、イポーリトの面差しには、ゆるぎない覚悟と決意の色こそ明確に浮かんでいたが、先刻まで見え隠れしていた利己心や恍惚感は、今や完全に消え去っている。
次の瞬間、不意に、ベルムデスもイポーリトの傍に跪いた。
「ミカエラ様、まさしく、此度の戦さ、死戦を覚悟の戦いとなりましょう。
その者の申す通り、イポーリト様がご同行くだされば、戦士たちの士気は必ずや高まりましょうぞ。
本来ならば、ミカエラ様や皇子様たちを戦線に引き摺り出すなど、もっての他と深く心得てございます。
いっそのこと、戦さの間、敵の目の触れぬところに奥深く匿わせて頂きたい気持ちでございます。
ですが、このままでは、この陣営は打ち破られ、その果ては、ミカエラ様たちの御身を非常な危険に晒すことになりましょう。
それを防ぐには、ここにいる兵たちが、何としても勝たねばならんのです!」
そう言って、ベルムデスは、いっそう深々と地に傅(かし)ずいた。
「その者の申しますように、退路も絶たれ、物理的な兵力にも著しく劣る我らが勝機を掴むためには、いかに兵の士気を鼓舞できるか――今や、その一点にかかって参りましょう。
もちろん、わたしもイポーリト様のお供として参ります。
見た目は老いぼれていようとも、つい先日まで、トゥパク・アマル様と戦場に立っておりましたこの身、この腕、まだまだお役に立てるものと自負しております。
イポーリト様は、必ず、このわたしが命に代えてもお守りいたしますゆえ!」
「ベルムデス……!!」
そう、ミカエラとイポーリトが同時に声を漏らした時には、マリアノとフェルナンドも、イポーリトの傍へと駆け寄っていた。
「兄上、僕たちも一緒に参ります!!」
そんな弟たちの頭を優しく抱いて、その耳元で力強く言う。
「ありがとう、マリアノ、フェルナンド。
だけど、そなたたちは母上のお傍に残り、母上をしかとお守りしておくれ!
それに、ここに残る兵たちを励まし、力の源となっておくれ!!」
そして、今一度、ミカエラを敢然と見上げた。
「母上、お願いいたします!!」
ミカエラは、いっそう険しくなった目元を吊り上げて息子を見下ろしていたが、張り裂けるほどに大きく見開かれた瞳は激しく揺れている。

一方、イポーリトは、その年端に似合わぬ長身を翻して立ち上がると、挑むようにミカエラに詰め寄った。
「母上!!」
強い覚悟と決意を宿した息子の眼差しは、鬼気迫るほどに鋭利真剣で、ミカエラの視界の中で、まるで別人のようにさえ見える。
そして、瞬間、イポーリトの蒼い炎の燃え立つ目の中に、夫トゥパク・アマルを見た気がして、彼女はハッと息を呑んだ。
周囲の者たちもまた、ミカエラの答えを息詰めて待ちつつも、いざとなれば彼女を振り切ってでも飛び出していきそうな皇子の気迫に呑まれ、恍惚と静まりかえっている。
その静寂の中で、ミカエラは何かを吹っ切るように、きつく瞼を閉じた。
それから、決然とその目を見開く。
「―――わかりました」
今や、凛と見下ろす戦女神の如く麗しくも厳然たる面差しは、完全に私情を排した指揮官のそれである。
「イポーリト、そなたは奇襲部隊と共に行きなさい。
そして、何をも惜しむことなく、存分に戦ってくるが良い――!」

かくして、サンガララの本陣で、ミカエラたちが敵軍を迎え撃つための準備を緊急に進めている頃、当地を発った一羽の伝令鳥が、沿岸のトゥパク・アマル陣営へ舞い降りようとしていた。
強い気流に乗って時速200キロを超える高速でアンデス上空を降下し、英国艦隊を迎え撃つべく海岸線に布陣したインカ軍へとまっしぐらに滑空する伝令鳥。
その強靭な翼が、宙を切裂いていく。
スペイン軍の襲来を斥候たちから知らされたミカエラが、トゥパク・アマルに向けて即座に放った鳥である。
まだ姿を現さぬ英国艦隊と、数キロを隔てて対峙するアレッチェ率いるスペイン軍陣営とを交互に睨みながら、刻一刻と迫り来る大決戦に向けて厳重な臨戦態勢を敷くトゥパク・アマル陣営もまた、張り詰めた空気が漲っている。
その陣営の中心に、トゥパク・アマル本人の姿があった。
彼は、大海とスペイン軍の両者を最も良く見晴らせる陣営の一角に設(しつら)えられた野外の指令本部で、敵方の動きを報告するために入れ替わり立ち代り現れる斥候たちの報告に耳を傾け、必要な指示を淀みなく発している。
その時、高い天頂から、不意に、甲高い鳥の鳴き声がトゥパク・アマルの耳を貫いた。
(――!)
それは、とても遠く、微かな声であったが、彼は、それがミカエラの放った伝令鳥のものであることを瞬時に悟った。
と同時に、サンガララの本陣に異変の起こったことを即座に直観して、反射的に指先を握り締める。
これまでもトゥパク・アマルとミカエラは、遠隔地にありながらも、様々な伝達事項や情報の交換を頻繁に行ってきてはいた。
だが、そのための伝令文や書状は、専ら早馬による使者か俊足の飛脚たちによって運ばれていたのだった。
ミカエラ自身の判断力や統率力によって、あるいは傍に仕えるベルムデスの智慧によって、大概のことは解決されてきており、トゥパク・アマル自身も彼女たちの采配に信頼を置いていたため、これまでは陸路を経ての連絡で事は十分に足りていたのである。
そのような状況下、此度の突然の伝令鳥の飛来は、そのこと事態、本陣で並々ならぬ緊急事態の生じていることの証しでもあった。

(あのミカエラが、伝令鳥までよこすほどの緊急事態とは――)
それは、彼女の手に余るほどの強大な敵襲以外には、考えられなかった。
トゥパク・アマルは、にわかに内心に動揺を覚えたが、しかしながら、一触即発の緊張状態下にある当地の兵たちに、これ以上の不安を煽るわけにはいかなかった。
彼は、目の前の斥候が報告を終えて立ち去った機をとらえ、一見、何も変わったところのない表情と態度のまま、スッと立ち上がる。
「暫し、はずす。
皆の者にも、順次、小休止をとらせよ」
そのトゥパク・アマルの足元に、斥候たちを取り次いでいた隊長格の厳ついインカ兵が、「はっ!」と、敏捷に畏(かしこ)まった。
トゥパク・アマルは頷くと、その長身を翻し、己を囲んでいた衛兵や斥候たちの集団から足早に離れていく。
他方、やはりミカエラの伝令鳥に気付いていた護衛のビルカパサが、トゥパク・アマルと同様に嫌な予感を直観したまま、やや距離を保ちながら主の後を追う。

トゥパク・アマルは陣営の中心部から離れ、岬の突端に歩んでいった。
岬の下方から吹きつける強い潮風が、彼の長い漆黒の髪と黒マントを荒々しく宙に巻き上げる。
その風の中で、彼は伝令鳥に向かって高く腕を差し伸べた。
そして、地上の獲物に襲いかかる猛禽類の如く、瞬速で急降下してきた鳥を、その強靭な腕でガシッと受け留める。
それから、鳥の脚に結び付けられた布を手早くほどいた。
伝文の記されたその布を視線で辿るトゥパク・アマルの厳しい横顔に、苦渋の影が走る。
(やはり……!)
敵軍が山麓まで迫り来ていること、退路も無く、敵の約半数の兵力で迎撃するつもりであること――ミカエラの筆跡で簡潔に走り書きされたそれらの伝文を読み終える頃には、さすがのトゥパク・アマルも青ざめていた。
めったに見せぬその顔色の変化と、非常に険しい横顔でサンガララの方角を睨んだトゥパク・アマルの様子に、少し離れた場所に控えて見守っていたビルカパサは、ついに居た溜まれなくなって歩み寄った。
「トゥパク・アマル様、何か不味いことでも?」
「サンガララの本陣に敵軍が迫っている。
しかも、我が軍が、かなり劣勢な状況にある」
低く早口で答えたトゥパク・アマルの傍らで、ビルカパサも生唾を呑み込んだ。

その彼の視界の中で、トゥパク・アマルはサンガララの方へと向けていた険しい視線を水平線の彼方へと移していく。
次第に夕刻時が迫り、射し込む斜光を受けて反射する海面は、まるで無数の残酷な刃を敷き詰めているかのごとくに見える。
その光景を見据えながら、トゥパク・アマルは、早くも懸命に頭を巡らせはじめているのであろう。
彼の思慮深い切れ長の目の端が、いっそう鋭利に研ぎ澄まされていく。
だが、そんなトゥパク・アマルの握り締めた拳には、必要以上に力が入りすぎ、不規則に微動している。
そのさまに、ビルカパサは胸を掻き毟られる思いに憑かた。
(トゥパク・アマル様……!
ご本心では、今すぐにも、ミカエラ様や皇子様たちのおられるサンガララへと馳せ参じたいに相違あるまい)
その時、再びトゥパク・アマルの声が聞こえてきた。
「次第に暮れ時も迫っているが、英国艦隊は未だ姿を現さぬ。
このまま日が暮れれば、夜間の襲撃をしてくるとは考えにくい。
その裏をかいてくる可能性も皆無ではないが、いかに英国艦隊と言えども、このような不慣れな海域で無理に夜間の襲来を試みれば、座礁の危険があまりに大きい。
恐らく、海上で一夜を明かし、装備や編隊を整え、夜明けを待って押し寄せてくる心積もりであろう」

「それでは、当地での決戦は明朝以降になると?」
低く絞ったビルカパサの言葉に、トゥパク・アマルは厳然とした横顔で無言のままに頷いた。
それでは、トゥパク・アマル様、急ぎサンガララに援軍に向かわれますか?!――と、衝動的に喉元まで出かかったが、ビルカパサは己の言葉を呑み下した。
いかに当地での決戦が明日に持ち越されようとも、どれほど超人並みに馬を飛ばそうが、もう間もなく戦闘の火蓋が切られるであろうサンガララの決戦に間に合おうはずがなかった。
それどころか、たとえ一晩、ここから死に物狂いで馬を駆ろうとも、サンガララの山麓の末端にさえも辿り着けはしないだろう。
ビルカパサが様々に思い巡らせている間にも、宙を睨みつけたトゥパク・アマルの面差しには、激しく思考を働かせ続けているさまが見て取れる。
が、不意に、トゥパク・アマルの強靭な手の平が、自らの顔面を無造作に拭った。
続いて、その口の端から、声にならぬ苦渋の呻きが漏れる。
その様子に、ビルカパサは屈強な体躯を強張らせたまま、唇を強く噛み締めた。
――このトゥパク・アマルでさえも、此度ばかりは対応策を考えあぐねているのだ。
(トゥパク・アマル様……!)
やがて苦しげな面持ちをこちらに振り向かせ、トゥパク・アマルが言う。
「緊急に軍議を開く。
即刻、当陣営に残っている主だった隊長たちを集めよ。
ただし、一般兵たちには、このことを知らせてはならぬ。
今、いらぬ不安を煽るわけにはいかぬ」
「はっ、心得てございます。
それでは、すぐにも!」
太く答え、野性の敏捷さで走り去るビルカパサの気配を背後に感じながら、一人残ったトゥパク・アマルは吹きつける烈風の中で瞼をきつく閉じた。
その手は、無意識のうちに、荒々しく額を押さえ込む。
(今となっては、あまりに時が足りぬ。
だが、このままという訳にはいかぬのだ…何としても……!
ミカエラ――!!)

それから間もなくの後、トゥパク・アマルは、己の陣営にいる主だった隊長たち――アンドレスやロレンソは既に出陣しており、その場にはいなかったが――と共に、緊急の軍議の席にいた。
ただし、英国艦隊やアレッチェ率いるスペイン軍主力部隊との決戦を目前に控えた今、いらぬ不安を煽ることの無きよう、一般兵たちにはサンガララの敵襲について伏せられていた。
かくして、その場に会した十数名の隊長たちの誰もが、トゥパク・アマルの伝えたサンガララの状況に、愕然と息を呑んだ。
「それでは、ミカエラ様たちは、退却することもかなわぬと……!」
問いに頷くトゥパク・アマルは、今は一応の沈着さを取り戻してはいたものの、その表情には未だ深い沈痛さを拭えない。
だが、その声音は冷静さを通り越して、冷徹なほどであった。
「先日の豪雨で、退路としていた山側斜面の河川が氾濫し、今は渡れぬ状態になっている。
恐らく、敵方はそのことを見越した上で、襲撃を企図したのであろう。
英国艦隊の襲来も迫り、クスコでの決戦も火蓋を切った今、各地の戦線も激化しており、サンガララの兵力は著しく分散している。
この機に乗じて、急遽、我らの本陣に敵が矛先を向ける可能性は十分に予測すべきことであったというのに、そのことに対する配慮も備えも欠けていたわたしの失態だ」

「トゥパク・アマル様……!」
トゥパク・アマルの声音と口調こそ凍てつくほどの冷厳さを保ってはいたものの、そこに滲む悔恨と苦渋の気配の深さに、その場の誰もが激しく胸を突かれて凝固した。
しかし、今度は、そのような暗鬱たる空気を押し退けるように、再びトゥパク・アマルの声が厳然と響き渡る。
「だが、まだ本陣が破られたわけではない。
ミカエラやかの地の兵たちは、自軍の数の劣勢にもかかわらず、勇敢にも敵軍を迎え撃たんとしている。
恐らく、今頃は、決死の覚悟を固めていることであろう」
「おお…ミカエラ様……!!」
「トゥパク・アマル様、あの陣営には、イポーリト様、マリアノ様、フェルナンド様たちも…!」
トゥパク・アマルは重々しく頷き、机上に広げられたサンガララ周辺の地勢図を刃のごとく鋭利な目で見下ろした。
そして、渇いた苦々しい声で、口惜しげに言う。
「ミカエラや息子たちはもとより、側近の者たち、そして、これまで本陣を護ってきてくれた多数の尊いインカ兵や訓練中の義勇兵たちも当地にはいる。
一兵たりとも失ってよい者などいない。
できることならば、サンガララ周辺地域から、すぐにでも援軍を差し向けたいところであるが、ディエゴ率いるクスコ戦に多くの兵力が回っている上、この数日で戦線が急速に各地に拡大し、サンガララの本陣周辺には、距離的にも、兵力的にも、即座にミカエラたちの元に駆けつけられる援軍は無い」
その場に会した一同の間から、溜息とも呻きともつかぬ深い苦悩の息が漏れる。

さらに、トゥパク・アマルは、その強靭な褐色の指先で、スッと、図上をなぞった。
「あの急峻な山岳地に攻め込む優勢な敵を、その火力を封じながら迎撃する方法は、限られている。
恐らく、味方の部隊を分割し、一方の部隊は陣営に残って敵の侵攻を阻止し、他方の部隊は攻め上る敵軍を待ち伏せ、奇襲挟撃し、白兵戦に持ち込む心積もりであろう」
目元を険しく吊り上げて語るトゥパク・アマルの言葉に、周囲の者たちは色を失った顔をいよいよ強張らせながら、息を詰めた。
「トゥパク・アマル様…凄まじい肉弾戦になりますな……」
いっそう重々しく頷きながら、トゥパク・アマルは続けていく。
「さすがに、あの峻厳なサンガララの山を武装して登るには、敵方も予想以上に難儀していることであろう。
もう陽も大きく傾きだした時間帯ゆえ、このままいけば、夕刻時から夜間にかけての決戦になる。
敵方としても、本来であれば山麓でミカエラたちの軍を包囲したまま夜営し、夜明けを待っての襲撃としたいところであろうが、それではインカ側の援軍が到着するまでの時間をいたずらに稼ぐ結果となり、彼らにとっても不利。
なれば、夜間の決戦に雪崩れ込もうとも、我が軍の援軍が及ぶ前の今夜中に、何としても決着をつけたい気構えであろう」
一同は、青ざめて身をわななかせながら、トゥパク・アマルの言葉に暗澹と頷く。
そのような彼らの前で、トゥパク・アマルの口元から、苦渋に満ちた、しかしながら、決然たる声が放たれる。
「そこで、苦肉の策ではあるが、わたしに考えがある。
――だが、それまでにミカエラたちが持ちこたえてくれるものか……!」
そう宙を睨みつけて語るトゥパク・アマルの面持ちは、もはや修羅の形相であった。
